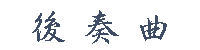 (2) その日、講義の終わった後、オラクルは大学のカフェテリアにいた。 「オラトリオと待ち合わせですか」 話し掛けられ、オラクルは緊張感を覚えた。クオータが突然、マンションを訪ねて来てから、数日しか経っていない。 「…何か用でも?」 「用事が無ければ、話し掛けてもいけないのですか」 クオータの言葉に、オラクルは口を噤んだ。クオータが負っているであろう心の傷の深さを思えば、毛嫌いするのは躊躇われる。それでも、どうしても理解する事が出来ない。 クオータは、片方だけの碧い瞳でじっと、オラクルを見つめた。明るい陽射しの中にいるので、髪も瞳も琥珀色に近い。肌は透けるように白く、とても柔らかそうだ。 ――あなたを…抱いてみたい… 「何、してんだよ、てめえ」 オラクルとクオータは、同時に声のした方に視線を向けた。オラクルが、優しく微笑む。 「私も此処の学生ですからね。カフェテリアを利用する権利くらいはあります」 「他にいくらでも、空いてる席があんだろうが」 言いながら、オラトリオはオラクルの華奢な肩に、手を置いていた。まるでクオータから、オラクルを護ろうとするかの様に。 「この間は、すみませんでしたね、オラクル」 言って、クオータは席を立ち、踵を返した。 「何なんだよ、この間って」 「…一昨日だったかな…。クオータが、急に家に来たんだ」 やや躊躇ってから、オラクルは言った。 「家って、俺達の家か?何で知ってやがんだ。それに、お前、そんな事、言って無かったじゃねえか」 「__ごめん…」 オラクルに俯かれ、オラトリオは後悔した。きつい言い方をしてしまった事を反省する。結局は、嫉妬なのだ。 「ともかく、帰ろうぜ。ちょっと寄りたい所もあるし」 きつい言い方の埋め合わせをする様に、優しく、オラトリオは言った。 寄り道した喫茶店で、オラトリオは椅子を引き、オラクルの背と腕に軽く触れて座らせた。そして、向かいの席に座を占める。眼が見えないからといって、そこまでしてやる必要は、無い。が、オラトリオは細かな事にまでオラクルの世話を焼くのが好きだった。二人が恋人同士になってからは、オラクルがそれを厭がる事もなくなった。 「サークルの先輩から、ここの紅茶がすごく美味いって聞いたんで、来てみたんだ。前にも話したと思うけど、カルマっていう…」 「紅茶にとても詳しくて、すごく奇麗な人って、聞いてたけど」 「ああ。あれで男だなんて信じらんねえぜ__ま、お前の方が奇麗だけどな」 オラトリオの言葉に、オラクルは微笑んだ。自分がどんな外見をしているのかは判らない。が、オラトリオが誉めてくれるのは嬉しい。 「お前も…とても奇麗なのだろうね」 二人の顔立ちに似たところがあると、ラヴェンダーから言われた事がある。従兄弟なのだから不思議は無い。シグナルは、オラクルの方が優しい顔だと言っていたが。 「奇麗って、普通、男に言わねえだろうが」 オラトリオの言葉に、オラクルは不思議そうに小首を傾げた。 「だって…お前はいつも、私にそう言うじゃないか」 「そりゃ、相手がお前だからだ」 余りに無邪気なオラクルの言葉に、照れくさく思いながら、オラトリオは言った。オラクルはまだ納得がいかないのか、不思議そうにしている。その白い頬に、オラトリオは触れ、オラクルはオラトリオの手に、自らの手を重ねた。 それにしても、クオータの事が気になると、オラトリオは思った。入学した当初からオラクルに横恋慕しているらしい。美しくはあるが、蛇の様に冷たい眼が、気に入らない。それにあの、顔の右半面の惨たらしい火傷跡。それが故に、眼の見えないオラクルに執着する気持ちは、理解できないでも無い。 だからと言って、赦せない事に、変わりは無いのだが…。 「何を表から見えるような場所でいちゃついとる」 怒気を含んだ声に、オラトリオは緊張を覚えた。琥珀色の瞳が、射る様に、彼を見据えている。 「やあ、コード」 穏やかに微笑んで、オラクルは言った。 「珍しい場所で会ったね。此処って日本茶も置いてるの?」 「茶を飲みに来た訳では無い」 「じゃあ、何をしに?」 むすっとして言うコードに、おっとりと、オラクルは聞いた。コードとオラトリオは、共にオラクルを見つめた。コードは、たまたま店の前を通りかかり、二人の様子を見過ごせず、入って来たのだ。それを、オラクルが本当に理解していないのか、或いはオラトリオを庇う為にコードを懐柔しようとしているのか、何とも判断しがたかった。 「…たまには紅茶を飲むのも悪くなかろう。道場の帰りで、喉が渇いた」 言って、コードはオラクルの隣に座った。口調は和らいだが、オラトリオを眇める眼は、変わらず厳しい。オラトリオとオラクルの仲を認めていない訳でも無いのに、オラトリオを”悪い虫”扱いする事は止めないのだ。まだ子供でしか無い妹達の周囲にも、そうやって眼を光らせているに違いない。 「ところでオラクル、この前の話だがな」 「ああ、あれ…。やっぱり、私には無理だと思う」 隣合って座る二人の会話に、オラトリオは幾分、穏やかならぬ気分になった。 ――この前って、何時だ?話って何だ? 「それでも、行って話を聞いてみるだけの価値はあろう。ひよっ子が、いつもお前の側にいられる訳でもなし」 自分の事に言及され、オラトリオは黙っていられなくなった。 「何の話なんです、師匠?」 「盲導犬だ」 オラトリオの方に斜めに視線を向け、コードは言った。 「前にも飼う事を勧めたがな。犬が怖いなどと言いおって」 「だって…」 少し拗ねたように、オラクルは言った。 「ストーカーが周りをうろついとるんだ。番犬は必要だろう。いつも側にいられる番犬が、な」 意味ありげな視線をオラトリオにちらと向け、コードは言った。どうやらコードにとって、オラトリオはオラクルの番犬らしい。 「クオータって奴のこってすか?そう言や、何度か無言電話が掛ってきたけど、あれもあの野郎の仕業だったのか」 「無言電話?」 「ああ。俺が出ると切れちまうんだ。回線が混線しただけかと思ってたが…」 聞き返したオラクルに、逆に、オラトリオは聞いた。クオータから、電話が掛ってきていないのかと。 「無いと思うけどな…。無言電話とかも、特に、無かったし」 おっとりと言うオラクルを、コードが心配げに見つめた。 「もっと警戒心を持つべきだ。お前は甘すぎる。世間知らず過ぎる」 コードの最後の言葉に関しては、オラトリオも同感だった。尤も、それを言うと、オラクルは厭がるが。 「だって、お前の言い方だと、世の中みんな、悪い人ばかりみたいじゃ無いか」 「人を見たら泥棒と思えという言葉を知らんのか」 「知らない」 きっぱりとオラクルに言われ、コードは言葉に詰まった。オラクルはとてもおっとりした性格なのだが、妙に頑固なところもある。ひと度、引かないと決めたら、決して、折れる事は無いのだ。尤もオラトリオは、常にオラクルに譲歩を与えてはいるが。 言葉を交わす二人の様子を見るうちに、オラトリオは落着かない気分になった。母親が違うせいか、コードとオラクルの外見や雰囲気に、似たところは無い。傍目には、兄弟には見えないのだ。 であるにも拘わらず、二人がとても親しいのは明らかだ。コードの瞳は、オラクルに向けられる時には柔らかな光を帯びるし、口調も、オラトリオに対するのとオラクルに向けるそれとでは、明らかに異なる。それで、オラクルは自分に話し掛けられているのだと、判断できる程だ。 一方のオラクルも__本人が意識しているか否かは別として__コードの腕や肩に親しげに触れる。そしてそれを見るたびに、オラトリオは落着かなくなるのだ。 「…ともかく、もっと自分の周囲に気をつけるのだな」 憮然と、だが微妙なニュアンスを込めて、コードは言った。 その日、帰宅した時に、ドアの前に花束があるのを見、オラトリオは不審に思った。取り敢えずそれを手にして、部屋に入る。 「お帰り、オラトリオ」 先に帰っていたオラクルが、いつも通り、優しく微笑んで、言った。いつも通り、オラトリオはオラクルに口づけた。そして、聞く。 「ドアの前に花束があったぞ、。何なんだ、これ?」 「…多分、クオータだよ」 躊躇いがちに、オラクルは言った。クオータが訪ねて来、この間のお詫びに、渡したい物があると言ったのだ。オラクルはドアを開けず、クオータを、中に入らせなかったのだと、オラトリオに話した。 「じゃあこれ、あの野郎が持ってきた花か__捨てちまおうぜ」 「何も…捨てる事は無いじゃないか。とても良い香りがするし」 眼の見えないオラクルの為に、クオータは薫りの良い花束を用意したのだろう。確かに、心地よい香りがする。整然と片付き、何の装飾も無く殺風景なこの部屋に、急に華やかさが増したようだ。オラトリオは、クオータに先を越される前に、自分がこういう花束を用意すれば良かったと、後悔した。 「…お前がそう、言うんだったら、リビングテーブルの上にでも活けとくぜ。花瓶は無えから、適当な空き瓶にでも」 そう、言ったオラトリオに、オラクルは微笑んだ。 その時、オラトリオの携帯が鳴った。オラクルは、紅茶をいれる為に席を立った。 「…だから、それはこの前も断ったじゃねえか__ああ…」 ティーポットにお湯を注ぐと、ダージリンの薫が立ち上った。 「来週も、来月も同じだ。…まあ、そういうこったな。悪ぃけど、諦めてくれ。じゃ」 オラクルは、ティーポットと2組のカップをお盆に載せ、リビングに戻った。誰からだったのか聞こうとして、躊躇う。 「サークルの奴からだった。コンパに顔、出せってうるさくてな」 オラクルが聞く前に、オラトリオは言った。 「行ってあげれば良いのに。せっかく、誘ってくれてるんだから」 カップに紅茶を注ぎながら、オラクルは言った。無論、本心などではない。心にも無い事を言っている自分に、オラクルは幾許かの嫌悪感を覚えた。無意識の内に俯いたオラクルの顎に、オラトリオは軽く触れて、上向かせる。 「俺はお前の側にいたいんだ。側にいられる時は、いつだって、な」 「でも…私はお前を縛りたく無い」 オラクルの瞳の色がうつろう。寂しげな表情。こうして一緒にいるのに、何故、そんな顔をする…? 「今更、何を言う。俺はお前の虜なんだぜ」 内心の軽い不安を笑いに紛らわせて言うと、オラトリオはオラクルに、口づけた。 ――あなたはオラトリオの事を、どれ程も、知ってはいない…最初でなければ、最後でも無い…きっと、後悔する… 「…どうしたんだ?」 辛そうに俯くオラクルの顔をまじかに覗き込み、優しく、オラトリオは聞いた。軽く額に触れる。熱は無い。体調が悪い訳ではなさそうだ。 「クオータとかいう野郎に、何か言われたのか」 思い付く事は、他に無い。オラクルは答えなかった。否定しなかった事が、肯定になっている。オラトリオは憤りを覚えた。 「何、言われたか知らねえが、あんな奴の言う事なんぞ、気にする事ぁねえぞ。お前に横恋慕して、勝手に嫉妬してんだからな」 あの野郎には気を付けろと、オラトリオは言った。いつもオラクルの側にいてやれたら良いと思い、それが叶わない事に軽い、苛立ちを覚えながら。 「講義室、変更になってますよ。一緒に行きましょう」 数日後、そう、オラクルはクオータに話し掛けられた。 「あ…あ。ありがとう」 言っては見たものの、少し、不審を覚える。いつも、同じ専攻の何人かに頼んで、休講や講義室の変更が掲示されていた時には教えて貰っている。その内の誰も、そんな事は言っていなかった。それに、クオータが花束を持って来たときに、ドアを開けなかった事で、クオータが怒っているかもしれないという不安もあった。 クオータは、オラクルの腕を軽く掴み、歩き出した。そうされるより、逆に腕を掴ませて貰う方が、オラクルには歩きやすい。が、大概の者は盲人にどう、対処すべきか判らないので、こうやって、腕を掴むのだ。オラクルは黙ったまま、クオータに従った。 来た事の無い場所だ。この大学のキャンパスはとても広い。初めての場所では、不安にならざるを得ない。それに、周囲に人気が感じられない。 「…何処なんだ、ここは」 そう、オラクルは聞いた。 「言いませんでしたか?講義室ですよ」 クオータはドアを開け、オラクルを中に入らせた。空気が篭もっている。光が感じられない。倉庫か何か、閉鎖的な場所だ。ドアを閉め、鍵を掛ける音が聞こえる。 「…騙したな…」 不安を覚えながら、そう、オラクルは言った。 「あなたと、二人きりになりたかっただけです。誰にも、邪魔されない場所で…」 オラクルは、眉を顰めた。不安が募る。不意に、クオータに両腕を掴まれた。振り払おうとするが、逆に、杖を奪われた。これでは、身動きが取れない。 「…どうする積もりだ…」 「想いを遂げたい__奇麗な言い方をすれば、ですが」 オラクルは、コードの言葉を思い出した。後悔しても、遅いのかも知れない。 「こんな事をして、何になると思っている…?」 「あなたが悪いのですよ。私を、拒絶し続けたから」 冷たく、クオータは言った。オラクルの恐怖が増す。 「…こんな事をしても、お前が得る物など、何も無い」 「そうでしょうか?」 形の良い口元を僅かに歪めて笑い、クオータは言った。 「これで少なくとも、あなたは私を忘れられなくなります。私の事を、考えない訳にはいかない。それが例え憎しみや怒りであろうと、私はあなたの心を占める事が出来る…」 歪んだ、強い感情。 オラクルは、恐怖に駆られ、腕を振り払おうとした。が、却って強く、腕を掴まれる。痛みに、オラクルは短く呻いた。クオータは、強引にオラクルに唇を重ねた。 「__痛っ…」 クオータの手の力が、僅かに緩む。オラクルに噛み切られた唇に、血がにじむ。その隙に、オラクルは相手から逃れた。が、すぐに捕らえられ、床に押し倒された。両手首を掴まれ、動きを封じられる。 「余り手間をかけさせないで下さい。それとも…痛めつけられたいのですか…?」 ――オラトリオ…! 心の内で、オラクルはオラトリオの名を呼んでいた。殆ど、叫ぶように。 講義が休講になったので、オラトリオはオラクルの通う大学に向かった。それは、彼らの住むマンションから歩いて行ける距離にあり、オラトリオの大学からは電車で20分、足らずだ。二人は、なるべく一緒に帰るようにしていた。子供の頃、オラトリオがいつも、オラクルを盲学校に迎えに行っていた様に。 特に最近は、オラトリオはなるべくオラクルの側にいるようにしていた。クオータとオラクルは大学が同じなのだから、顔を合わせない訳には行かない。コードの言っていたように、盲導犬でも飼った方が良いのかも知れない。 先に、食料を仕入れにスーパーに寄ろうかと、オラトリオは思った。今からならば、オラクルが受講している講義が終わるまで、1時間近く、ある筈だ。どうせ今日も、弟達が夕食時を狙って来るのだろう。 ――さて、今夜は何にすっかな 献立を考えながら、オラトリオはオラクルの事を想っていた。 「お前は…自分で自分を追い込んでいるだけだ」 やっとの思いで、オラクルはそう、言った。嫌悪感に、背筋が粟立つのを感じながら。 「…私が…?」 オラクルの首筋に舌を這わせながら、クオータは言った。 「お前が孤独なのは、周囲がお前を拒絶しているからでは無いよ。お前の方で、周りの人たちを寄せ付けないからだ」 「私が孤独がっているなどと、あなたは思うのですか?」 「私には、判る…」 クオータは、動きを止め、まじかにオラクルを見つめた。瞳の色が、微妙にうつろいでいる。 ――家族など要らない。友人など要らない。欲しいのはただ、一人だけ… 「私があなたに心を開けば、あなたも私を理解してくれる…と?」 「少なくとも、今よりは__」 「私は、あなたに友人になって欲しい訳ではありませんよ」 冷たく笑い、クオータは言った。 「…そんな事…」 「ええ。無理なのは判っています。2年以上の間、ずっとあなたを見てきたから。あなたが想うのはオラトリオの事ばかり…。だから、あなたに愛されるのは諦めました」 言ったでしょう?そう、クオータは続けた。 あなたから愛されるのが無理なら、あなたに憎まれたい。それで、あなたの想いを私に向けさせる事が出来る。あなたの、心を占める事が出来るから… 「お前は…私を理解していないよ。私は、お前を憎んだりしない…」 「何をされても?__まるで天使ですね。そんな言葉、信じられません」 「そうじゃ無い…」 クオータに押さえつけられている腕の痛みに僅かに眉を顰めながら、オラクルは言った。 「誰かを憎めば、自分の心を傷つける事になる。だから…私は誰も憎まない。誰も、憎みたく無い…」 憎しみは、人の心を強くする。拒絶される事への恨み。憐れみで、貶められることへの怒り。その全てに、憎む事で対処して来た。かろうじて、誇りだけは失うまいと足掻いてきた。孤独と疲労とを自覚しながらも…。 一人暮らしを始めた頃、昔、出て行った母親が訪ねて来た時の事を、クオータは思い出した。自責の念に耐えられなかったのだと、彼女は言った。我が子の火傷の跡を見るたびに、そして、それが惨たらしいが故に、見るのが耐えられなかったのだ、と。そんな火傷を負わせてしまった自分の責任の重さに、耐えられなかったと…。 ――私を…赦して… ――可笑しな事を言いますね。私は、あなたを憎んでも、怨んでもいません ――憎んでいない…? ――ええ。私は、あなたに関心など、無いのです… 何の関心も持たない事。この上ない、拒絶。かつて、自分を見放した相手への報復__。 憎しみは、人の心を強くしたりなどしない。ただ、相手を傷付け、自分を傷つけるだけ。だから憎むのは止めた。最愛の者であったが故に、激しく憎んだ。そしてそれが自らの心をずたずたにした。孤独と疲労の果てに、無関心である事を選んだ。誰に対しても、何に対しても。 ――それでも、誰かにいて欲しい。ただ一人で良い。たった一人で… クオータの手から、力が抜けるのを、オラクルは感じた。 ――周囲がお前を拒絶しているからでは無いよ。お前の方で、周りの人たちを寄せ付けないから… クオータは、黙ったまま、オラクルを見つめた。視線が合う。それでも、オラクルの瞳にクオータの姿は映らない。オラトリオの姿も、誰の姿も。 「__あなたは…オラトリオを憎まずにいられるのですか?もし、彼があなたを裏切っても」 「…憎まないよ。オラトリオを憎むなんて、出来ない」 「裏切られても?彼が、あなたを、厄介な重荷としか見做さなくなっても?」 「耐えられない、そんな事…」 言ってしまってから、オラクルは後悔した。口にしたのは本心だった。クオータに、誰かに聞かせるべき事ではない。それでも、止められなかった。 「そうなっても、オラトリオを憎んだりは出来ない。そうなっても…私はオラトリオを愛さずにはいられない…」 オラクルの声が、幽かに震える。クオータは、思い知らされた。オラクルの心の全てを、オラトリオが占めている事を__少なくとも、今は。 「__オラトリオは…幸せな人ですね」 そう、クオータは言った。 「あなたのような人に、これ程、想われているなんて…」 クオータはオラクルから手を放した。 オラクルの講義が終わるまで暫く待っていようと思い、オラトリオはカフェテリアに行った。そしてそこの窓際のテーブルに、オラクルとクオータが座っているのを見たのだった。 「…オラトリオ…」 オラトリオが話し掛ける前に、オラクルは気配に気づき、そして微笑んだ。 「お前んとこも、休講になったのか?」 聞きながら、オラトリオは面白くない気分だった。オラクルが何故、クオータなどと一緒にいるのか、それが、理解できない。 「そんな所だよ。帰ろうか?」 言って、オラクルはオラトリオの腕に、軽く手を添た。クオータは何も言わなかった。ただ、二人が立ち去るのを、じっと見つめていた。 シグナル達が来るまでには、まだ大分、時間があるだろう。リビングのソファに座るオラクルの隣に、オラトリオは席を占めた。 ――何故、あんな奴と一緒にいた?警戒してる筈じゃ無かったのか?周囲に人がいれば手出しもして来ねえだろうが、だからって… 「…オラトリオ…?」 問いかけに答えないオラトリオに、オラクルは不審そうに呼びかけた。オラトリオは、自分がオラクルの話を聞いていなかった事に気づいた。 「何で、あんな奴と一緒にいた?クオータの事だ」 思い切って、オラトリオは聞いた。 「何でって…」 オラクルは、当惑げな表情を浮かべた。オラトリオは、クオータが花束を持ってきた時に、オラクルがドアを開けなかったと言っていたのを思い出した。オラクルが、それ程、強い拒否を示す事は珍しい。つまりそれは、最初にクオータが突然、此処を訪ねてきた時に、何かがあったからでは無いのか?クオータが来ていた事を、オラクルがオラトリオに話さなかったのも、そのせいでは無いのか? 疑惑と嫉妬とが、オラトリオを衝動に駆り立てた。オラトリオはオラクルに口づけ、そのままソファの上に押し倒した。 「オラトリオ…」 オラクルの驚きを、オラトリオは無視した。服の上からオラクルの身体を愛撫し、耳たぶから首筋にかけ、唇を這わせる。そして、シャツのボタンを外しにかかった。 「オラトリオ、厭だ。こんな所で__」 「良いだろう?誰も来やしねえぜ」 コードがここの合鍵を持っている事は、オラトリオには大いに不満だった。が、コードは緊急用だと言って、譲らなかった。取り敢えず、鍵の他にチェーンも掛けてある。それに此処のリビングは、玄関から直接は見えない。 オラクルの、華奢な肩と、白い腕がむきだしになる。その腕に痣があるのを見、オラトリオは眉を顰めた。 「どうしたんだよ、これ。痣になってんじゃねえか」 驚いて聞いたオラトリオに、オラクルは答えなかった。オラトリオは相手のシャツを全て脱がせた。両腕と両手首に、痣がある。誰かに、強く掴まれたのだ。それが誰かなぞと、聞くまでも無かった。カフェテリアで見かけたとき、クオータの唇に血がにじんでいたのを、オラトリオは思い出した。 「お前、あの野郎に…」 低く、オラトリオは言った。強い嫉妬が、彼の感情を揺さぶる。クオータの唇が切れていたのは、オラクルが抵抗したからだ。他に、何をされた…?聞きたくは無い。聞いても、オラクルは答えないだろう。 強い感情に駆られるまま、オラトリオはオラクルを愛撫し続けた。幾分か、乱暴に。 「此処じゃ、厭だってば。オラトリオ__」 「お前は俺のものだ」 言ってしまってから、オラトリオは後悔した。まるで、オラクルの意志を顧みていないかの様だから。嫉妬が、浅ましい感情であるのも判っている。それなのに、それに振り回されてしまっている。何があったにせよ、オラクルは被害者なのだ。不当な八つ当たりもいいところだ。 「…私はお前のものだよ」 静かに、オラクルは言った。 「髪の毛の一筋にいたるまで…」 オラトリオは手の動きを止め、オラクルを見つめた。視線が合う。一緒に暮らすようになってから、視線の合う事が多くなった。オラクルには何の意味も無い事なのだろうけれども、その度に、オラトリオの心が騒ぐ。 「私の心を占めるのは、お前だけだ。いつも、そして、どんな時にも…」 オラクルはオラトリオの頬に触れ、濃い金色の髪に、細い指を絡めた。 「そして、お前は私のもの。お前の心を占めるのも、私だけだと信じている…」 「オラクル…」 私の全てをかけて、お前を愛すると、オラクルは誓った。それは、言葉だけの事などでは無いのだ。 ――これ程、愛されてて、それも判んねえのかよ、お前は… オラトリオは、オラクルに口づけた。乱暴な振る舞いを詫びるかのように、とても優しく。そして、オラクルを抱き上げた。 その後、オラクルがクオータに悩まされる事は無くなった。同じ講義を取る時に、クオータがいつもオラクルの隣に座る事は変わらなかったが。
|
